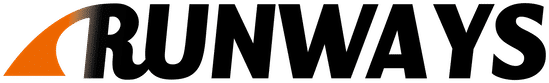INTERVIEW

個人にとって合理的な判断をすると、社会の利益を損なってしまう「社会的ジレンマ」。環境問題のような地球規模の課題から、日常生活で遭遇する身近なトラブルまで、根底にはこの構造が潜んでいるケースは少なくない。
立正大学経営学部経営学科の山本仁志教授は、社会モデリングやシミュレーションによって、社会的ジレンマや、利他行動の仕組みなどを分析し、社会をより良くする規範のあり方、仕組みづくりなどを研究している。
人間はなぜ、金銭や時間などのコストを使って他人に利益を与える利他行動をとるのか、社会全体の利益につながる選択を人々がとるようにするためには、何が必要なのか。社会的ジレンマの基本から、我々の身近にある課題解決のヒント、今後の社会において必要な規範などについて、話を聞いた。

山本仁志:立正大学経営学部経営学科教授
電気通信大学大学院 情報システム学研究科博士後期課程 修了
日本数理生物学会、日本人間行動進化学会、日本社会心理学会、社会情報学会所属
世の中の課題に潜む「社会的ジレンマ」の構造
ー最初に、先生の現在の研究の概要について教えてください。
山本:私は現在、社会的ジレンマなどをテーマに、シミュレーションや被験者実験を用いていろいろな社会現象のメカニズムを解き明かす研究を行っています。
例えば環境問題はなかなか解決ができない大きな社会の課題です。CO2削減やSDGsの目標達成は、技術的、制度的な対策ももちろん大切ですが、別のアプローチとして、社会を構成する人々や企業、自治体などの行動を分析し、どういうルールがあれば社会全体のプラスになるような行動をとるのか、課題の構造を紐解くことも解決の糸口につながる可能性があります。そうしたことに興味を持ち、今の研究に携わるようになりました。
ー社会的ジレンマとは一体どのようなものなのか、基礎的なところを教えていただけますか。
山本:社会的ジレンマというのは、一人一人の個人が自分にとって利益がある、合理的だと思われる判断をすると、社会全体で見たときにデメリットが生じてしまう問題です。身近な例でいうと、例えばごみ捨てですね。それぞれの住民は、ごみが家の中にあるのは嫌なので、ごみが出たら都度部屋の外に捨てたいけれど、地域社会としては、決まったごみ捨ての日を住民が守らないと、ごみ捨て場に常にごみがある汚い街になってしまいます。
いま、私たちの社会にはいろいろな課題がありますが、その中には、この社会的ジレンマの構造が眠っているものも数多く存在しているんです。
そして、個人と社会の利害の対立がある社会的ジレンマの構造がある場合に、どのような仕組みや制度、仕掛けがあれば、個人の利益ではなく社会全体の利益を大きくするために皆が協力するのか、それを探るというのも私の研究テーマの一つです。私たちはこれを「協力の進化」と呼んでいます。
ー先生の研究における「協力」というのは、どのような行動を指すのでしょうか。
山本:この研究でいう「協力」というのは、例えばお金や時間・労力といった自分の資源を手放して相手に利益を与える、利他行動のことです。
協力することで自分の資源を失ったとしても、使った資源よりも協力によって相手が得た利益の方が大きければ、全員が利他行動をとることで社会全体としての利益はプラスになります。しかし、協力するかしないか、それぞれの人が自由に決めることができる社会では、必ず協力しない人が出てきます。なぜなら、「人には協力してもらうけれど、自分は協力しない」、「協力によって社会が得た利益は自分も享受するけれど、自分は資源を払わない」という戦略が、自分だけのことを考えると一番得するからです。
ーなるほど。まさに社会的ジレンマですね。
山本:そうですね。しかし、私たち人間は、さまざまな理由から自分の資源を使って他人に利益を与えます。身近な例だと、募金なども利他行動の一つと言えるでしょう。「情けは人のためならず」という言葉があるように、利他行動というのは実際の社会の中では往々にしてあるんです。特に人類は、こうした相互の協力をものすごく大規模に成立させたからこそ、地球上で繁栄できたとも言われています。
人間だけにみられる「間接互恵」とは
ーそのような利他行動をとるのは、人間だけなのでしょうか?
山本:実は人類だけではなく、人以外の動物、例えばネズミなどにも自分の分を相手にあげて相手を助ける利他行動がみられるんです。
人間以外でみられている利他行動は、「直接互恵」、いわゆる恩返しですね。つまり二者間での、助けてくれたから助けてあげるという行動です。これはもちろん人間でもみられるもので、シンプルで発生しやすいタイプの協力といえます。
直接互恵のほかにもう一つ、「間接互恵」というものがあります。これは人間にしかみられない協力の形で、二者間ではなく、第三者が登場します。例えば私が誰かを助けたとします。それを見ていた第三者が、「山本さんはあの人を助けていたから、良い人なんだ。今度、山本さんが困っていたら助けてあげよう」と考え、また利他行動を取るという協力の形です。そしてさらに、それを見た誰かが「あの人は山本さんを助けているから、今度あの人が困っていたら助けてあげよう」というふうに協力が広がっていきます。
「あの人は良い人だ」という評判を介して、協力がつながっていくんですね。こうした利他行動が間接互恵です。これは社会が存在しないと成立しないものです。このような評判を介した、間接互恵が成立するのは人間だけだと言われています。
ー間接互恵は人間にしかないということですが、私たちはどういうときに間接互恵となる協力をするのでしょうか?
山本:間接互恵がちゃんと回っていくためには、何が良くて何が悪いかを判断するルールがあり、そのルールに従って、あの人は困っている人を助けたからいい人だ、あの人は助けないから悪い人だ、という評判が必要になってきます。このルールが、いわゆる社会規範といわれているものですね。
社会や集団によって規範の内容はさまざまです。例えば、ある業界では、何か間違っていることがあったら、それをはっきり指摘するのが、そこで働く人たち共通の規範だとします。しかし、その業界ではビジネスを回すためにその規範がうまく機能しているとしても、もしかしたら全く別の友人同士のグループでは、少しの間違いを都度指摘すると、あの人はきついとか冷たいという評判につながってしまうかもしれません。
コミュニティの中で規範が共有されていないと、良かれと思ってやったことが悪いと判断され、協力がループしなくなってしまいます。規範が共有された状態が、社会規範が成立してる状態といえますね。
ー利他行動を人々が取りやすくするためには、この行動はプラスです、この行動は良くありませんというルールが認識されている必要があるのでしょうか?
山本:そうですね。ただし、どういう行動を良いとするのか、どのようなルールがあれば協力が安定的に起こるかというのは、実は簡単そうにみえて非常に難しいんです。
例えば、助ける行動がGoodで助けない行動がBadという規範があるとします。この場合、うまく機能するためには、いい人の場合は助ける、逆に悪い人の場合は助けないという基準が必要になります。この基準に則って行動すると、例えば悪い人を見かけても、基準に従ってその人を助けません。しかし、この助けないという行動を見た他の人は、助けない行動はBadという規範があるため、「他人を助けなかったこの人は悪い人だ」と認識してしまいます。非協力が簡単に連鎖してしまうんです。この「助けるはGood、助けないはBad」という規範は、理論的には、非常に脆弱だということがわかっています。
さまざまな社会規範が社会の中で生成し共有されていく過程そのものは、完全にはわかっていません。私も規範の成立過程をシミュレーションによって分析しましたが実験的裏付けなど課題が多く残されています。間接互恵のメカニズムにはまだまだ解明されていない部分が多くあるんです。
利他行動が広がり、よりうまく回る社会にするためには、そのコミュニティに属している人々の特性や文化、時代背景などがうまくマッチした規範を作る必要がありますが、特に現代は、それがより難しくなっているといえると思います。
おそらく社会の変化がゆっくりであれば、その変化に従って社会が徐々に規範を動かして、うまく機能する形に作り上げていくと思うんです。しかし今は、変化が激しい時代です。しかも、インターネットの普及やグローバル化で、異なる規範を持った人たちがいろいろなところで何重にも重なっています。インターネット上では、自分の主張が正しいと思っている人たち同士の喧嘩が頻繁に起きていますが、これは異なる社会規範を持った人たちが混在した状態であることも一因ではないでしょうか。
ー素人の立場としては、仕組みがわかっていればできそうな気がしてしまったのですが、実際には簡単ではないんですね。
山本:そうですね。社会的ジレンマ自体が、協力するよりも協力しない方が個人としては必ず得をするという根本の構造を持っています。何か策を講じても、例えばどうにかして協力せずに利益を得るという抜け道のような手法でずるをする人が出てしまいがちなんです。だからこそ社会課題はなかなか解決しないし、解決してもまた次の課題が出てくるのだと思います。
「評判」が、人々の行動を左右する
ー先ほど、間接互恵は「あの人は良い人だ」という評判を介して協力行動が広がると伺いましたが、例えば誰も見ていなくても、自分が良い行動を取ることで社会全体が良くなり、その良い社会に身を置くことが自分にとっても利益となるという力学で、評判を介さなくても協力行動が広がることはないのでしょうか。一例ですが、仕事の現場では、家庭の事情などで早く帰らなければいけない人がいると、残った社員がその人の仕事を手伝うということがよくあります。フルタイムで働けない人の仕事を快く手伝うことで、将来自分にも育児や介護など早く帰らければいけない状況が起こったときに、同じように助けを得ることができるという暗黙の了解があるのではないでしょうか。
山本:まさに間接互恵の事例だと思いますが、このケースで間接互恵がうまく機能するためには、「あの人は快く仕事を引き受けている、他人を助けている」という評判が必要だと思います。その評判があるからこそ、「あの人が帰りたいときは私が助けてあげよう」という第三者による協力が生まれるのであって、恐らく完全匿名で誰が助けたのかがわからない状態だと、間接互恵が生まれづらくなるのではないでしょうか。
もちろん、誰も見ていなくてもいいことをしよう、誰かを助けようという考え方の人もいるとは思いますが、集団の人数が多くなればなるほど、全員がそうした考え方をするというのは無理があります。もし誰が助けたかが全くわからない状態になった場合、「自分は助けないけれど自分が困ったときには助けてもらう」という人が出てきてしまうんです。なぜなら、助けていないことがばれない以上、その人が最も得をするからです。
私も助けていますよと言いながら本当は助けないという戦略をとれば、全くコストを支払わずに利益だけを受け取ることができてしまいます。おっしゃったような事例の場合は、完全な匿名状態をキープしてしまうと、いずれはそういった戦略をとる人間が生まれて、力学的には仕組みが崩壊してしまうと思います。
ーなるほど、確かに、評判は人々の行動を左右する大事な要素なんですね。
山本:私たち人間は、ものすごく評判を気にする生き物だと言われています。人類学の世界的権威であるダンバーという学者が、カフェテリアなど人の集まる場所で、人々の間で交わされる会話を記録して分析するという実験をしたのですが、その結果、人々のコミュニケーションのおよそ7割が社会的情報の交換、要は誰かの噂話だったそうです。私たちは、誰かと会話する時間のうちかなりの部分を、評判の交換に費やしているんですね。お互いに評判を交換して、あの人はこういう人だという認識を持っていることが、コミュニティを成立させるために必要で、恐らく私たちは無意識のうちに、ものすごく評判というものを意識しているといえると思います。
ー先生は、利他行動の動機、その根源にあるものとは一体何だと思いますか?
基本的には、自分が生き残るための行動だと思います。生き残ることができない行動だとしたら、利他行動をとる生き物は淘汰されているはずです。協力する生物が淘汰されずに生き残っている以上、やはりそこに何か、利他行動をとった方がプラスになるというものがあると考えています。
問題の構造を知り、異なるアプローチで解決を
ー改めて、先生の研究の一つである「協力社会の進化」を実現させることで、私達の実際の社会にとってどのようなプラスがあると考えられるでしょうか?
山本:協力、利他行動が全くなくなってしまったら、おそらく人類は滅びてしまいますね。ある意味、社会の基盤、いわゆる重要なインフラといえると思います。どのようなプラスがあるかというよりは、人類が生き残るためにはこの協力し合う社会を維持していく必要があります。今後の社会においては、いかに少ないコストでストレスなく、相互の協力を維持していくのか、そのためにどのような仕組みを作るのかがとても大事になってくるのではないでしょうか。
実際に我々が暮らす世の中で、社会的ジレンマの構造を理解し課題解決につなげる活用の仕方としては、一見、個人の心の中や教育、道徳などに問題の原因があると捉えがちな場面において、別の側面からアプローチする一つの手法とすることができるのではないでしょうか。そこに社会的ジレンマの構造がないかをちょっと立ち止まって考えることで、解決の糸口が見えてくるかもしれません。
例えばいじめを見かけても、見て見ぬふりをしてしまうというのはよくある問題だと思います。いじめという悪い行動をなくすためにはそれを放置せずに注意したりやめさせたりすることが必要ですが、自分はいじめないけれど、注意するのはいやだ、と考えてしまう人は多いのではないでしょうか。
悪い行動はしないけれど、悪い行動を止めたり罰したりするコストは負担したくない、これは「二次のジレンマ」と呼ばれています。規範を守らない人を罰するコストを誰が負担するのか、というのは実はいじめに限らず多くの場面で見られる問題なんですね。
仮に、いじめが起きているコミュニティで、問題の根底にこの二次のジレンマの構造があるとしたら、いじめを見て見ぬふりをする人に対して、勇気を持とうと道徳的に呼びかけてもあまり効果はありません。なぜなら見て見ぬふりをする方が得だからです。
だとしたら、いじめはやめようと声を上げる方が得する仕組みを構築したり、注意するコストを担う信頼できる存在を作ったり、異なるアプローチが解決につながるかもしれません。
さまざまな問題に対して、実はこうした構造があるのではないかとニュートラルに考えることが、実際の社会でこの社会的ジレンマの考え方を生かす方法の一つだと思います。
ー確かに、いろいろな社会課題に対して、視点を変えたアプローチをすることで、解決の糸口が見えるかもしれませんね。今後、深掘りしたい研究テーマや関心をお持ちの分野がありましたら教えていただけますでしょうか?
山本:今後は、人工知能(AI)の活用が広がっていくことが明らかです。現在は、人間のサポートとしての活用が主な使い方ですが、近い将来、AIと人間が混在するような状況が出てくると思います。例えば、人間の行動をAIが評価するというような時代がやってくるとしたら、AIが人間を評価する際の規範、どのような評価ルールをAIに搭載すべきなのか、もしくは善し悪しに関するAIの規範はどのようにしていくのが適切なのか、いろいろと検討すべき問題があると思います。もしかしたら、AIが判断することによって、人間の規範そのものも変わっていくこともあるかもしれません。AIと人間が混在した社会の中で必要な社会規範について、しっかりと扱っていきたいと考えています。
ー人間がAIの評価をどう受け止めるのか、非常に興味深いですね。
山本:人間はAIに対して、バイアスがかかった見方をすることがあるといわれています。よくあるのが「アルゴリズム嫌悪」と「アルゴリズム礼賛」という、二つの逆方向のバイアスです。
ある研究者が、人事が採用者を選ぶという場面で、女性のほうが多い応募者の中から、AIと人間の人事担当者がそれぞれ応募者を採点するという実験を行ったんです。実験ではAIも人間の人事担当者も男性より女性のほうに一貫して低い得点をつけます。すると実験の参加者は、人間の選択に対してよりネガティブな反応をしたんです。つまり、女性が多いにもかかわらず、なぜ一貫して女性に低い点数をつけたのか、そこに差別的な動機があったのではないかという受け止め方ですね。
一方で、同じ選択にも関わらず、AIの選択に対してはそのようなネガティブな反応が抑えられていました。AIが選んだんだから、差別なんてしないだろう、公平に判断してより良い人材を選んだんだろうと受け止めていたんです。これはアルゴリズム礼賛の一例ですね。同じ結果に対して、その結果を出したのが人間かAIかで、我々は違う受け止め方をしてしまう可能性があると考えられます。
このようなAIの判断を過剰に信じてしまうアルゴリズム礼賛、逆にAIの判断なんて信じられない、人間に判断してほしいというアルゴリズム嫌悪があると言われていますが、どういうメカニズムで発生するのかは、実はよくわかっていません。
AIと人間が混在していく社会の中で、こうした評価に対する人間の受け止め方、メカニズム、そして必要な規範などについて、今後取り組んでいきたいとなと思っています。
ー最後に、読者に向けて、改めてメッセージをお願いできますか。
山本:社会的ジレンマというと、一見馴染みがなかったり、身近ではない問題と感じたりしてしまうかもしれません。しかし、社会的ジレンマや協力の進化というものは、まさに私達の日常生活、皆さんが生きている環境そのものの問題です。
なかなか解決しない問題や、何かおかしいと感じることがあった際に、一回立ち止まって、社会的ジレンマのような構造がないか、共有しているルールにはどのようなメリットデメリットがあるのかといったことを考えていただけると、もしかしたら解決のヒントが眠っているかもしれません。ぜひ興味を持っていただいて、世界を見る一つの新しい眼鏡のように、見方を変える、解像度を上げるツールの一つとして使ってもらえるとうれしいですね。